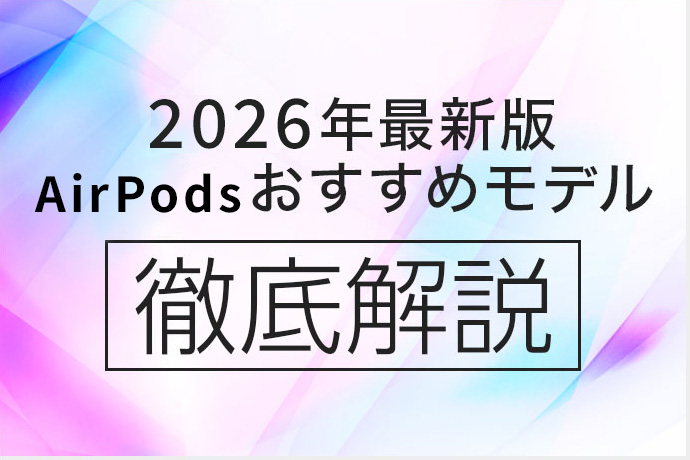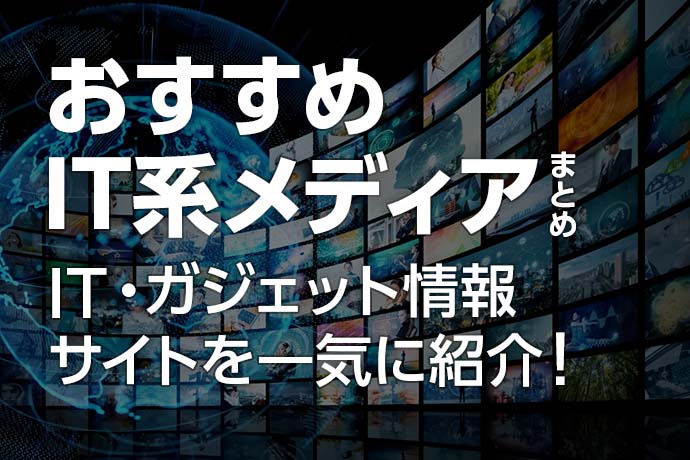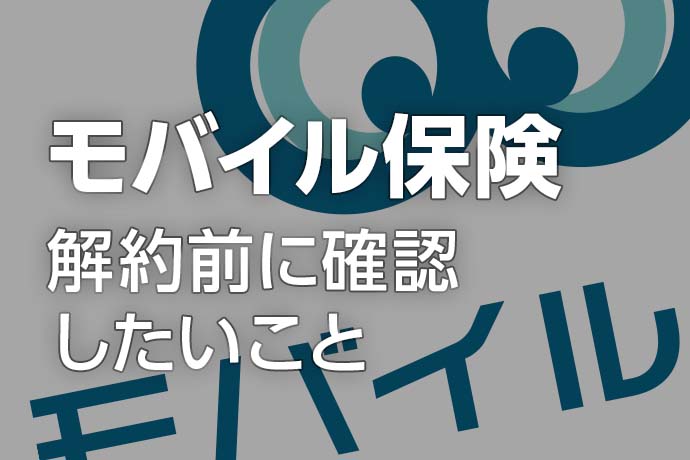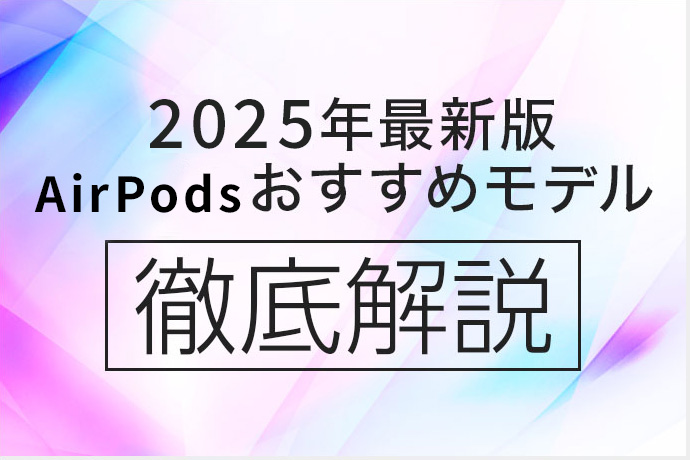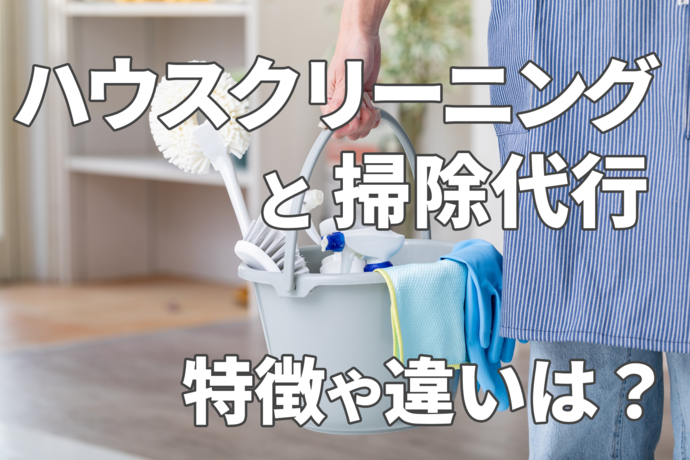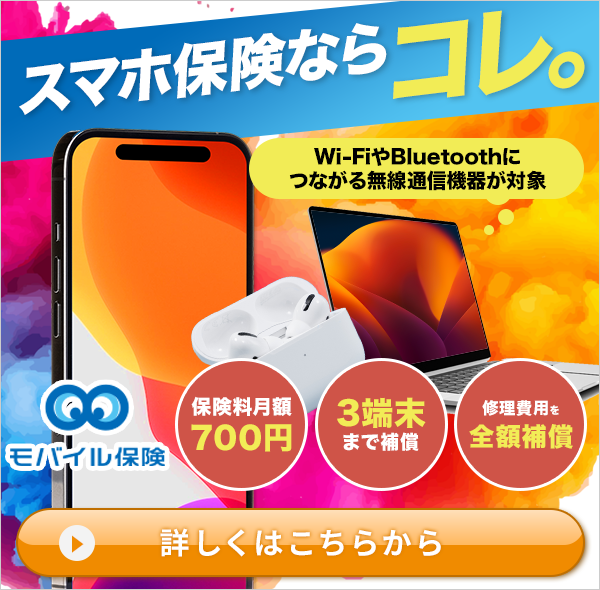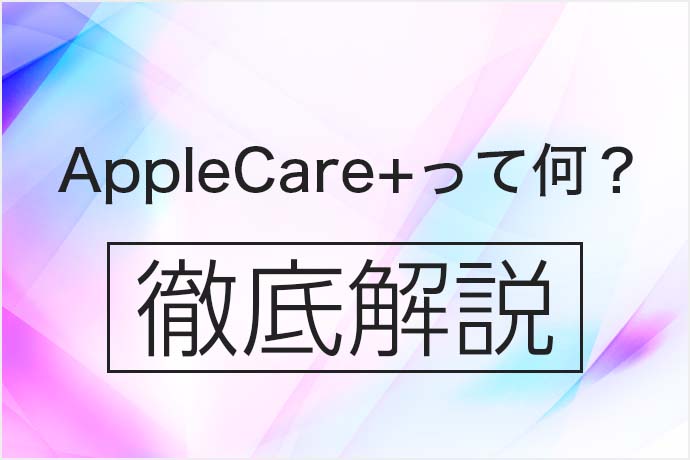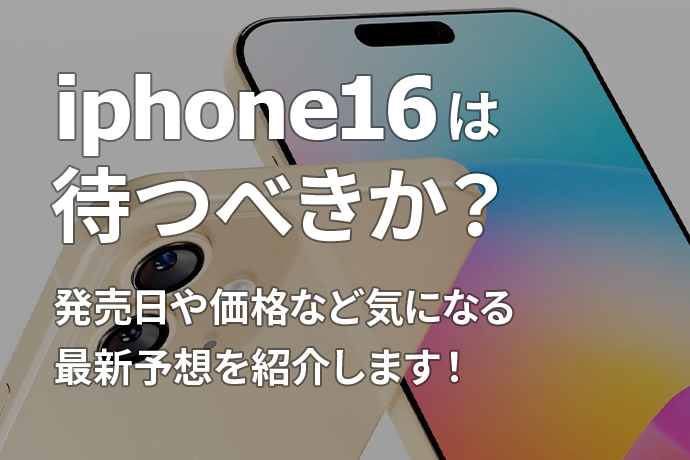マイナ保険証に関する6つの疑問! 登録方法や使い方、不安を感じるポイントについて詳しく解説します!
- 2025年01月16日
- その他
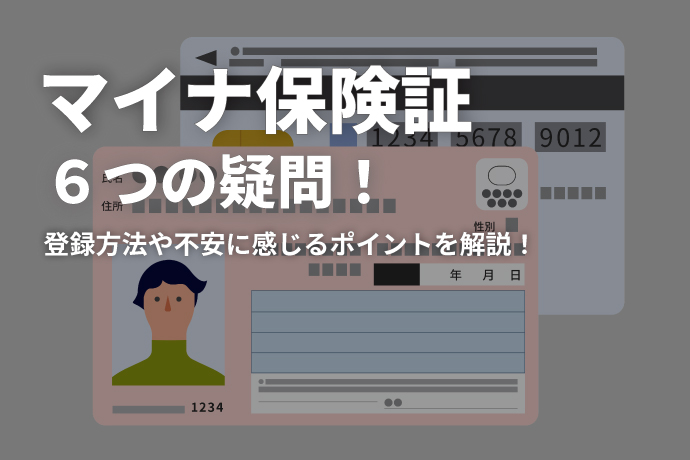
2024年12月2日より、マイナ保険証の利用を基本とすることになりました。
マイナ保険証の運用自体は2021年10月よりスタートしていますが、移行がなかなか進んでいないために、マイナ保険証の利用を半ば必須とする仕組みになりました。
この移行が進んでいない背景には、マイナ保険証に切り替えるメリットや必要性、使い方など、様々な疑問があるものと考えられます。
そこでこの記事では、マイナ保険証に関する主な疑問について、解説していきます。
利用を迷っている方や不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として使用する仕組みのことです。
また、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードのことを指す場合もあります。
マイナ保険証を利用することで、過去に処方された薬や特定検診の情報を閲覧することができるようになるため、より適切な診療を受けることが可能になります。
また、確定申告時に医療費控除が簡単に行えるようになる、手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払が免除されるなど、様々なメリットがあります。
ただ現時点ではトラブルが少なくないことも事実です。
機械の不具合により情報を読み取れないことや、高齢者などにとっては操作が難しい場合があることなどが挙げられ、まだまだ課題があるように感じられます。
国が今後の基本となる仕組みとしているものであり利用することは正しいはずですが、安易に切り替えて満足するのではなく、トラブルの事例やその対処法も把握しておくことが望ましいといえそうです。
- より適切な診療を受けることができる
- 限度額以上の一時支払いが不要
- 確定申告時の医療費控除が容易に
- 保険証の切り替えを待たずに利用できる
- システムや機械の不具合で利用できなくなる可能性がある
- 公費負担受給者の情報は紐づけされていない
- 高齢者にとっては操作が難しい場合も
マイナ保険証を利用したくない!問題はある?
マイナ保険証の運用自体は、2021年10月からスタートしていましたが、利用率はなかなか上がりませんでした。
利用するメリットにあまり分かりやすいものがないため、単に従来の慣れ親しんだ保険証をそのまま使い続けていただけという人も多いのではないかと思います。
一方で、マイナ保険証の利用に不安を感じるという人も少なくありません。
具体的には、セキュリティや個人情報の保護、システムトラブル、医療機関での対応などが挙げられます。
従来の保険証が利用できなくなってしまう以上、マイナ保険証を利用しなければ療養の給付を受けることができなくなってしまいます。
不安の一部は、どのような仕組みなのかやトラブルが起きた時の対処法を知ることで、ある程度解消できます。
折り合いをつけていくためにも、気になる点については調べるなどして理解していくのがよいのではないでしょうか。
マイナ保険証のセキュリティ・個人情報の保護
マイナ保険証のセキュリティ面のリスクを不安視する声は少なくありません。
マイナンバーカードは本人確認書類の1つで、保険証以外にも、住民票をはじめとする公的な証明書の発行や証券口座開設などの民間のオンラインサービスで利用することができるなど、非常に効力の強いカードです。
そのため紛失や盗難、不正アクセスといったリスクが大きく、そもそも持ち歩くことに不安を感じる人がいるのは無理もないことだといえます。
また、個人情報が集約され一元的に管理されるようになるという点もポイントです。
政府や第三者からの監視やプライバシーの侵害がないかという不安や、個人情報の漏洩リスクの増大などが懸念されます。
これらは制度や仕組み自体に対する不信感といえます。
これまでは従来の保険証を利用することで回避できていましたが、今後は折り合いをつけていくしかないのが残念なところです。
システムトラブル・医療機関での対応
マイナ保険証の利用シーンに関する不安もあります。
最も大きいのはシステムトラブルです。
紐づけのミスや負担割合の誤りなど様々なミスが報じられており、適切に運用されるのかどうか、気づかず不利益を被ることがないのか、不安を感じるのも無理からぬことでしょう。
他にも、医療機関に訪れた際に不具合や読み込みエラーが起きた場合どうすればよいのか、医療機関はちゃんと対応してくれるのかどうかなど、不安を感じるポイントは多々挙げられます。
こちらはセキュリティと違って、実際に現場で起きている問題なので、時間はかかるかもしれませんが改善は進められるでしょう。
自分がトラブルに合うことがないよう、自衛のために多少なりとも知識をつけられるとよいかもしれません。
マイナ保険証の登録方法は?
マイナ保険証の利用には、事前登録が必要です。
登録の方法は3通りあります。
医療機関・薬局で登録する
マイナ保険証を利用することになる医療機関・薬局で登録が可能です。
カードリーダーがあるので、手間はかかってしまいますが受診する当日その場でも登録することができます。
認証さえスムーズにいけば、画面に従って進めていくだけの簡単な手順となっています。
- マイナンバーカードを読み取り口に置く
- 認証方法を選択し、認証を行う(顔認証か暗証番号か)
- 「マイナンバーカードを保険証として利用するための登録が必要です」と表示されるので、「登録する」を選択する
- マイナポータルの利用規約を確認し、問題なければ「同意して次へ進む」を選択する
- 登録完了
マイナポータルからオンラインで登録する
マイナポータルで初回登録が可能です。
あらかじめ登録を済ませておくことで、医療機関でスムーズに受付できます。
- マイナポータルにログインする
- ホーム画面の「証明書」内の「健康保険証」を選択する
- 「マイナンバーカードを健康保険証として登録する」にチェックを入れて、「登録」を選択する
- 登録完了(マイナンバーカード利用が「登録済み」と表示されます)
セブン銀行ATMで登録する
医療機関・薬局以外では、現状セブンイレブンのセブン銀行ATMでのみ登録が可能です。
スマホやオンライン環境がない中で、あらかじめ登録を済ませておきたい場合には利用してみるとよいでしょう。
- セブン銀行ATMで「各種お手続き」を選択
- 「マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込み」を選択
- 利用規約を確認して「確認」を押す
- マイナンバーカードを挿入
- マイナンバーカードの暗証番号を入力する
- 登録完了
医療機関でマイナ保険証をちゃんと使えるか不安…
医療機関で実際に利用する際に、問題なく使えるのか、トラブルが起きないか不安という人も少なくないかと思います。
事前に手順やトラブルの事例を確認しておくと安心できるのではないでしょうか。
利用方法自体は簡単です。
まだ登録をしていない場合には登録手続きも必要になりますが、利用時の手順は認証を行うだけなので迷うことはないかと思います。
ただ、現場でトラブルが多発しているのも事実で、多数の事例が報告されています。
単なるトラブルでその場で解決できる類のものであればよいですが、中には「資格情報が読み取れず、料金が10割負担になる」など不利益を被るものもあります。
「認証エラー」や「マイナ保険証の有効期限切れ」などもあり得るので、従来の保険証が有効なうちはこちらも持ち合わせておくとよいでしょう。
スマホを保険証代わりにできる?
マイナンバーカードを保有している場合、利用しているスマートフォンにスマホ用電子証明書の搭載をすることができます。
マイナポータルから申し込みでき、銀行・証券口座の開設や携帯電話申し込みといった民間オンラインサービスの利用や、コンビニで各種証明書の交付を受けることなどが可能です。
健康保険証としての利用については、今後対応が予定されているものの、2025年1月現在では開始されていません。
電子証明差搭載サービス自体、Androidスマホのみの対応でiOSは準備中という状態ですので、長い目でリリースを待つことになりそうです。
資格確認書と資格情報通知書って何?
マイナ保険証を補助する書類として、「資格確認書」と「資格情報通知書」があります。
これらは別の書類で使用する場面も異なりますが、名前が近く混同してしまいがちです。
いざ使用するときにトラブルにならないよう、しっかりと区別をつけておくことが望ましいといえます。
資格確認書とは
マイナンバーカードに代わって、保険資格を有することを示すことができるのが「資格確認書」です。
医療機関や薬局でこの書面を提示することで、これまで通り3割負担で診療を受けることができます。
発行の対象となるのは物理的にマイナ保険証を利用できない状態の人で、マイナンバーカードを発行していない人、保有はしていてもマイナ保険証の利用登録をしていない人、マイナンバーカードの電子証明の有効期限が切れている人が含まれます。
申請も不要で勝手に送られてくるというのはありがたいところですが、現在のマイナ保険証周りのトラブルの多さを鑑みると、郵送の漏れや遅延といったトラブルが起きるのではないかという懸念があります。
資格情報通知書とは
「資格情報通知書」、もしくは「資格情報のおしらせ」とは、保険資格の基本情報が記載された書面です。
カードリーダーの不具合などでマイナ保険証の受付がうまくいかなかった場合に、マイナンバーカードとともに提示することで保険適用してもらうことが可能になります。
「資格確認書」との違いは、単独で利用できるかどうかです。
「資格確認書」はマイナ保険証の代わりになるもので、単独で使用が可能であるのに対し、「資格情報通知書」はマイナ保険証のトラブルを回避する補助的な書面で、単独での利用はできません。
まとめ
マイナ保険証に関する疑問とその答えをまとめていきました。
整備されれば便利な制度ではありますが、現状ではまだトラブルが目立つ点が気になるといったところでしょうか。
医療機関などの現場でも、本来のメリットとして示されていたスタッフの事務コストが減るという点に反した結果になっているようです。
今後の改善に期待したいところです。