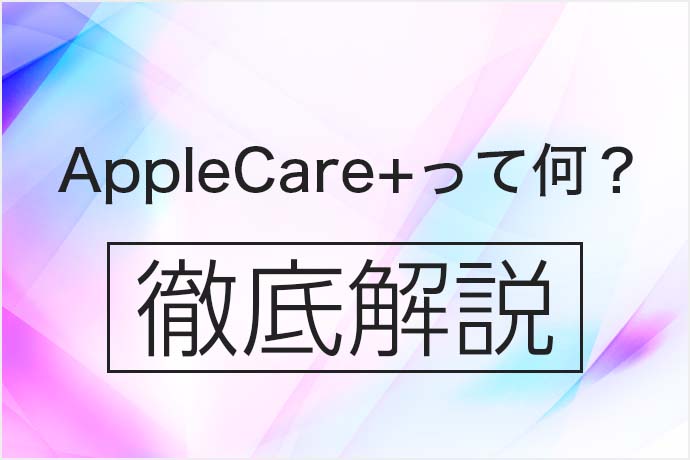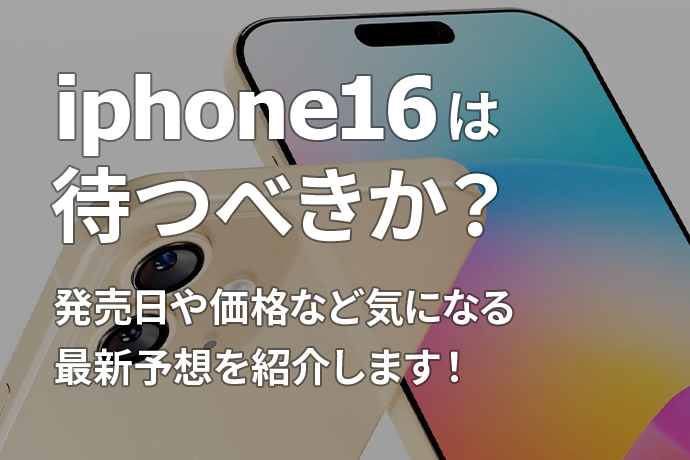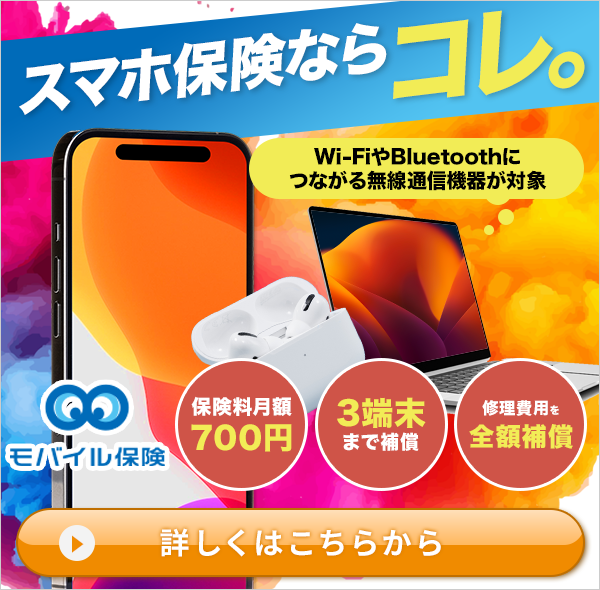iPhoneは何年使える?寿命の目安・買い替えタイミング・長持ちさせるコツを解説
- 2025年11月19日
- iPhone

多くの人が毎日のように使っているiPhone。
便利な一方で、「そろそろ買い替え時かな?」「何年くらい使えるものなんだろう」と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。
iPhoneの寿命は“何年で壊れる”といった単純な話ではなく、ハード面(バッテリー・部品)とソフト面(iOSアップデート)の両方から考える必要があります。
さらに、使用環境やメンテナンス次第で、同じ機種でも寿命は大きく変わってきます。
この記事では、iPhoneが実際にどのくらい使えるのか、
そして買い替えの目安や長持ちさせるコツについて詳しく解説します。
これからiPhoneを買い替えるか迷っている人や、できるだけ長く使いたいと考えている人の参考になれば幸いです。
目次
iPhoneの寿命はどのくらい?
iPhoneは耐久性に優れた精密機器ですが、永遠に使えるわけではありません。
平均的に見ると、3〜5年ほどが快適に使える期間といわれています。
ただし、「寿命」といっても突然動かなくなるわけではなく、バッテリーの劣化やOSのサポート終了、部品の老朽化など、複数の要素が重なって少しずつ使いにくくなっていくのが実情です。
ここでは、ハード面とソフト面の両方から、iPhoneの使える期間を整理します。
ハード面から見た寿命(部品・バッテリーなど)
ハード面の寿命を左右する最大の要因はバッテリーの劣化です。
Appleの最新情報では、iPhone 15シリーズ以降は理想的な条件下で「1000回」のフル充電サイクル後も最大容量80%を維持、iPhone 14シリーズ以前は「500回」が目安とされています。
同じサイクル回数でも、温度や充電習慣によって劣化速度は変わります。
この最大容量の80%というラインは、Appleがバッテリーを劣化したと認める基準となっています。
これを下回っているとiPhoneが十分なパフォーマンスを発揮できない可能性があり、AppleCare+に加入している場合には無料でバッテリー交換を受けることもできるようになります。
- iPhone 15シリーズ:1000回のフル充電で最大容量80%を維持
- iPhone 14以前:500回のフル充電で最大容量80%を維持
- 高温環境を避け、充電上限設定や「バッテリー充電の最適化」を活用すると劣化を抑えられる
ソフト面から見た寿命(iOSアップデート対応)
iPhoneの「使える期間」を考えるうえで欠かせないのが、iOSアップデートの対応期間です。
Appleはおおむね発売から5〜6年間、セキュリティを含む主要アップデートを提供しています。
たとえば、2020年に発売されたiPhone 11シリーズは、2025年秋リリースのiOS 18までサポート対象となっています。
一方で、2019年発売のiPhone XS・XRは、2024年のiOS 18が最終アップデートでした。
このように、ハードが問題なく動いていても、OSのサポートが終了すれば最新アプリが使えなくなったり、セキュリティリスクが高まったりします。
そのため、「実質的に安全・快適に使える期間は5〜6年程度」と考えるのが現実的です。
買い替えの目安と判断ポイント
iPhoneは耐久性やサポート面に優れており、長く使えるスマートフォンです。
しかし、性能が落ちたり部品が劣化したりすると、徐々に「そろそろ買い替え時かもしれない」と感じる場面が増えてきます。
買い替えのタイミングを感じさせるサインは、「動作」や「バッテリー」、「部品」など複数の要因から現れます。
性能がまだ十分に感じられても、iOSのサポート切れや修理費の高さを考慮すると、長くとも5〜6年をひとつの区切りとして新しい機種への移行を検討するのが現実的です。
動作の遅さ・不安定さ
アプリの起動が遅くなったり、画面が固まったりするのは、処理能力の低下やストレージ容量の圧迫が原因であることが多いです。
特に最新のiOSにアップデートしたあとに動作が重く感じる場合は、チップ性能が最新環境に追いつかなくなっているサインといえます。
アプリやウェブサイトが開けない、動画再生中に落ちるといった不安定な挙動が続く場合に、初期化やデータ整理を行っても改善しないようであれば、買い替えを検討したほうが良いでしょう。
バッテリー・充電関連の不調
バッテリーは時間とともに劣化していくため、充電の減りが早くなったと感じたら注意が必要です。
最大容量が80%を下回ると、1日の使用を持たせるのが難しくなるケースもあります。
また、充電が途中で止まる・過熱する・ケーブルの角度で接触が変わるなどの症状がある場合、コネクタ部分の摩耗や内部部品の劣化が進行している可能性もあります。
iPhone本体の損耗が少なく、もう2~3年使えるという判断であれば、買い替えではなくバッテリー交換で対応することも検討できます。
特にAppleCare+に加入している場合には、劣化の状況次第で無料で交換してもらうことも可能です。
- フル充電しても1日もたない(バッテリー最大容量が80%以下)
- 充電中の発熱やケーブル接触不良が頻発する
- モバイルバッテリーや電源接続なしでは不安を感じる
カメラ・通信・部品トラブル
カメラのピントが合わない、スピーカーの音が割れる、Face IDが反応しないといった、明確に一部の機能が正常に働かない状態になることが増えてきた場合も、買い替えを検討すべきサインです。
これらは経年劣化によるハードウェア故障であり、修理で直る場合もありますが、複数の部品を交換するとなると費用が高くつくことがあります。
修理費と新品の価格を比較したときに差が小さい場合は、買い替えのほうが結果的に満足度が高くなるでしょう。
- Face IDやカメラなど基幹部品の修理費が高額になる場合
- 複数の不具合(通信・音声・タッチなど)が同時に発生している
- すでにiOSのサポートが終了している
iPhoneを長く使うためのポイント
iPhoneはもともと耐久性の高い製品ですが、使い方次第で寿命は大きく変わります。
バッテリーやストレージの管理、ソフトウェアのメンテナンスを意識することで、同じ端末でも1〜2年長く快適に使い続けることが可能です。
iPhoneを長く使うためには、日常的なメンテナンスの積み重ねが重要です。
とくにバッテリーとストレージの管理は、快適な動作を維持するうえで最も効果が大きいポイントといえるでしょう。
バッテリーを劣化させない使い方
バッテリーの健康状態を保つには、温度・充電頻度・設定の3点を意識することが重要です。
iPhoneのリチウムイオンバッテリーは高温環境に弱く、真夏の車内や直射日光下での充電は劣化を早める原因になります。
また、充電回数を減らすために「使い切ってから充電する」のは逆効果です。
残量が20〜80%の範囲でこまめに充電するほうがバッテリーへの負担を軽減できます。
iPhone 15シリーズ以降では、充電上限を80%に制限できる設定や、使用習慣に合わせて充電を制御する「バッテリー充電の最適化」機能が搭載されています。
これらを有効にすることで、バッテリーの劣化スピードを抑えることが可能です。
- 高温・低温環境での充電を避ける
- 残量20〜80%の範囲でこまめに充電する
- 「バッテリー充電の最適化」をオンにする
- 充電しながらの長時間使用を避ける
ストレージ管理・データ整理
ストレージ(保存容量)が不足すると、動作が重くなったりアプリが正常に起動しなくなることがあります。
不要な写真やアプリを削除するのはもちろん、iCloudや外部ストレージを活用してデータを整理することがポイントです。
定期的な整理でストレージの空きを10〜20%確保しておくと、動作の安定性を保ちやすくなります。
設定アプリの「iPhoneストレージ」から、どのアプリがどのくらい容量を使っているかを確認できるため、使用頻度の低いアプリを一時的にオフロード(削除してもデータ保持)するのも効果的です。
- 写真や動画はiCloudや外部ストレージに移す
- 不要なアプリ・キャッシュを定期的に削除する
- 「iPhoneストレージを最適化」を有効にする
- 常に容量の10〜20%以上を空けておく
定期的なメンテナンス・OS更新
iPhoneを安全に長く使うためには、ソフトウェアの更新も欠かせません。
最新のiOSには不具合修正やセキュリティ強化が含まれており、古いバージョンを使い続けるとリスクが高まります。
またOSが古いままの場合、新しいアプリが動作しなかったり、今まで使っていたアプリがアップデートで使用できなくなったりすることもあります。
UIが変わるのを嫌がってiOSのアップデートをしない人もいると思いますが、定期的に更新していくことが望ましいでしょう。
- iOSを定期的にアップデートする
- 再起動を週1回程度行いキャッシュを整理する
- 使わないアプリを削除して処理負荷を軽減する
- セキュリティアップデートを必ず適用する
iPhoneを買い替えるなら?選び方とおすすめタイミング
買い替えのタイミングをうまく見極めることで、費用を抑えつつ満足度の高い選択ができます。
価格変動やキャンペーンの傾向を把握し、最新機種と旧モデルの違いを理解しておくことが重要です。
新モデルが登場するタイミング
Appleは毎年9月に新型iPhoneを発表し、1週間前後で販売を開始します。
この時期は前世代モデルの価格が下がる傾向があり、最新機能にこだわらない人にとっても旧モデルを最も安く入手できる時期でもあります。
春から初夏にかけては、家電量販店やキャリアが学割や乗り換えキャンペーンを展開することも多く、条件次第では新モデルをお得に購入できるチャンスになります。
- 9月の新モデル発表直後(旧機種が値下がり)
- 春〜初夏のキャンペーン期(学割・乗り換え特典)
- 年末年始のセールや下取り強化期間
最新モデルにこだわらない選び方
1〜2世代前のiPhoneでも、日常的な使用には十分な性能があります。
iPhone 13やiPhone 14でも、最新のiOSでも快適に動作し、写真撮影やSNS、動画再生などの用途では差を感じにくいでしょう。
Apple公式の整備済製品やキャリアの下取りプログラムを利用すれば、保証付きの端末を割安で購入できます。
中古市場でも状態の良い個体が多く、予算を抑えたい人には現実的な選択肢です。
ただ、iPhone 15以前のモデルはApple Intelligenceに対応していません。
今後ますます充実するであろうAI機能を利用することができないので、機種変更をするのであれば、最新にこだわらないとしてもiPhone 16以降を選ぶ方が望ましいかもしれません。
- iPhone 16以降のモデルならApple Intelligenceも利用できる
- 公式整備済製品は新品同様の品質で保証付き
- 中古端末は状態やバッテリー容量を必ず確認
買い替え時に活用したい下取り・保険
古いiPhoneは、Apple公式の「Trade In」プログラムやキャリアの下取りで還元を受けられます。
状態が良ければ数万円分の割引が適用されることもあり、買い替え費用を抑える有効な方法です。
さらに、モバイル保険やAppleCare+に加入している場合、修理・バッテリー交換後に下取りに出すことで、査定額を高く保てることがあります。
端末を丁寧に使うことが、結果的に次の購入時のコスト削減につながるのです。
- 下取り額を次の購入費に充てられる
- 保険で修理費を抑え、査定額を維持できる
- 整備済製品や保証付き中古で安心して再利用できる
まとめ
iPhoneは平均して3〜5年、長い人では7年近く使い続けることも可能な端末です。
ハード面ではバッテリー交換による延命ができ、ソフト面ではAppleが5〜6年間のiOSサポートを継続しているため、他のスマートフォンと比べても寿命が長い傾向があります。
ただし、バッテリーの劣化やiOSのサポート終了、修理費の高さなどを考慮すると、5〜6年をひとつの区切りとして買い替えを検討するのが現実的です。
動作が不安定になったり、最新アプリが使えなくなったりする前に新しいモデルへ移行すれば、より快適な使用環境を維持できます。
また、充電方法やストレージ管理など、日常の扱い方を工夫することでiPhoneはさらに長く使えます。
正しいメンテナンスを行いながら、必要に応じて下取りや保険を活用することが、結果的にコストを抑えながら長く使い続けるコツといえるでしょう。